飲み屋での即興憲法話が『日本国憲法を口語訳してみたら』の原型です。
愛知大学4年 塚田 薫
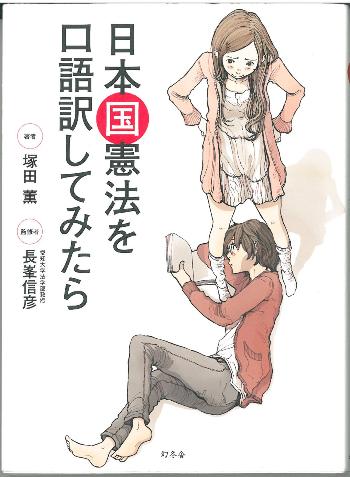
■『日本国憲法を口語訳してみたら』
出版社:幻冬舎 1155円 著者:塚田薫 監修:長峯信彦 カバーイラスト:浅野いにお
まず初めに僕がみなさんに申し上げたいことは、僕は「若者」の代表ではない、ということです。
「若者」に代表なんてものが存在するかどうかも僕は怪しく思っています。
もちろん平均像というものは存在するかもしれませんが、例えば、ある集団の平均身長が176cmだということがわかったとしても、その集団を構成する個々人の身長を把握することはできません。そもそもその集団に身長が176cmジャストの人がいる保障もありません。
ですので、僕は、どこにでもいる、ありふれた、固有の24歳です。
憲法を「口語訳」するという試みは、そんな若者の個人的な思い付きから始まりました。正直に申し上げますと、若者を啓発しようとか、憲法を守ろうとかは考えていなかったし、今でも考えていません。ただそこがミソであるとこっそり思っています。
飲み屋で、なんとなく「法学部で憲法を専攻している」と言いました。
当然、「?」となります。公民科の焼き直しをやってしまいそうになりましたが、酔っていてはかないません。そこで勢いにまかせて喋った即興憲法話が、『日本国憲法を口語訳してみたら』の原型です。
ところで、僕は常に自分の考えを語るときは、一人称を主語に語りたいと考えています。我々若者は、我々名古屋市民は、我々日本人は、我々アジア人は、でもなく僕は、です。
また、僕は徹底した個人主義者でありたいと願っています。個人主義は、憲法学的に重要な概念でありますが、時折、日常レベルではエゴイズムと混同されがちです。これらはいかに区別できるのでしょう。
憲法学者である長谷部恭男先生は、著書『憲法 第五版』(新世社・2012年)で次のように仰っています。
「個人は、それぞれ自分の考えるところに従って自分の生き方を決め、それを自ら生きるという点で、根源的に平等な存在である。」(162頁)
「自律した個人といえるためには、何よりも自分で「考える」ことが必要である。」(194頁)
もし、このような生き方がエゴイズムであるなら、僕は喜んでエゴイストになりましょう。
個人であろうとするには、相手も「根源的に平等な」個人として扱う必要があります。それをしなければ、それこそ僕はエゴイストになってしまうでしょう。これが決定的な違いです。
個人主義と平等とは、日本国憲法で国家の基本として明確に定めれていることです。そしてこれは普遍的な倫理ではないでしょうか。
例えば、キリストは人類はみな神の前では等しく罪人であると語り、「汝の敵のために祈れ」と教えました。
福沢諭吉の「天は人の上に人を作らず」や、キング牧師の演説("I have a dream"のあれ)も同じ精神を持つものでしょう。
しかし、先人の理想は未だに達成されているとは言いがたいのが現状です。倫理や道徳が、倫理や道徳として存在しているということ自体が、人間は縛らなければどこまでも逸脱してしまう存在であることの証明であるのかもしれません。
人間が集まっている以上、ユートピアなんてものは期待できません。
「理想など絵空事だ」
憲法についての本を出して以降、このような意見に接することが多々ありました。僕もそう思います。
「真面目に勉強すればいい暮らしができる」が、絵空事であるのと同じように、諦めて学校へ行かなければ満期除籍になります。
「人権などお花畑だ」
と仰る方もいます。僕もそう思います。そこに咲いているのは彼岸花です。過去の死や苦痛や血にまみれた土地に咲くのは彼岸花でしょう。
先人が築いてきたものは、絵空事でお花畑です。しかしそれらは甘っちょろい感傷でも書生論でもなく、ひたすら合理的で血が通ったものです。
その価値を人に伝えようとするのであれば、理想や理念としてではなく、便利に使える戦術として扱うべきものです。
「憲法を口語で」というコンセプトが多少なりにも目新しいものとして受け入れられ、それまで興味のなかった人達の目を引けたのは、こういったところに理由があるのではないかと考えています。
世界史でやったドイツのポーランド侵攻や、微分積分などが面白くてしょうがないと感じられた人はそんなに多くはないでしょう。同じように公民や政治経済で「勉強」をした憲法も、先生がなんか言ってたな、くらいのものにしかなっていないことが多いのが現状です。
しかし学校でやったことに興味を持てないから、というレベルでなく、最近の若者は社会に対して無関心であるということが言えるかもしれません。例えば投票率は20歳代が最も低く、平成に入ったころからかなり低下しています。
夏目漱石の『こころ』で、従来の価値観が近代化により崩れていく明治~大正に生きた個人をこのように表現しました。
「自由と独立と己れとに充ちた現代に生れた我々は、その犠牲としてみんなこの淋しみを味わわなくてはならないでしょう」
僕は平成元年に生まれました。windows95が発売された年に小学校へ上がり、インターネットの広がりと成長を同じくにして育ったわけです。
僕はチャットで世界中の暇人とお喋りをして、youtubeで好きな音楽を見付けて、SNSで24時間誰かと繋がれます。
それでも夏目漱石の「淋しみ」に共感します。
平成は、バブルの崩壊から始まり、経済力に支えられていた社会構造が大きく揺らいだ時代です。例えば今は亡き社会党から首相が出たのもこの時期です。
ずっと上をむいていたベクトルが、バブルの崩壊という天井にぶつかり、それぞれバラバラな方向へ散っていったと見ることができます。いわば、個人がより個人化した時代ではないでしょうか。
個人が個人化し、それらが繋がれるインターネットという技術が全盛の現代で、僕は孤独です。個人が個人として社会に繋がる手段が存在せず、点と点で繋がれても面はできません。それが淋しいのです。
僕と同じような「淋しみ」を感じる人達なのか、ここ数年、インターネット上で民族主義「のようなもの」を掲げ、排外主義的な主張をしていたグループが、ネットの外に進出しています。いわゆるヘイトスピーチ問題です。
民族や国家に帰属しているという感覚は、孤独を簡単に癒してくれるからかもしれません。
また、去年から今年にかけて、児童ポルノを規制する法律が改正されるにあたって、ネット上では大きな反対運動が起こりました。ロリコンが集まって騒いでいたという問題ではなく、規制の範囲がアニメや漫画に及び、それも取り締まり当局の恣意的な基準で違法とされかねないものであるとされたからです。
弁護士など法律関係者、アニメ・漫画関係者、そしてネットの住民が声を挙げました。
ネットの住民達にとっては、それは大事な趣味であると同時に、他人と繋がるための共通言語だからではないでしょうか。
このように個人の個人化の時代にあって、個人と国家の関係を定めた憲法は大きな意味を持つでしょう。ただ、憲法は目的ではなく手段なのであり、憲法があるからといってなにもかもオッケー!なんてことはなく、頭でっかちにならず考え続けることがなにより大事であると僕は思います。僕のように元々良くない頭で半端に勉強をすると頭でっかちになってしまいいけません。構えず、ゆるやかにやっていきたいものです。